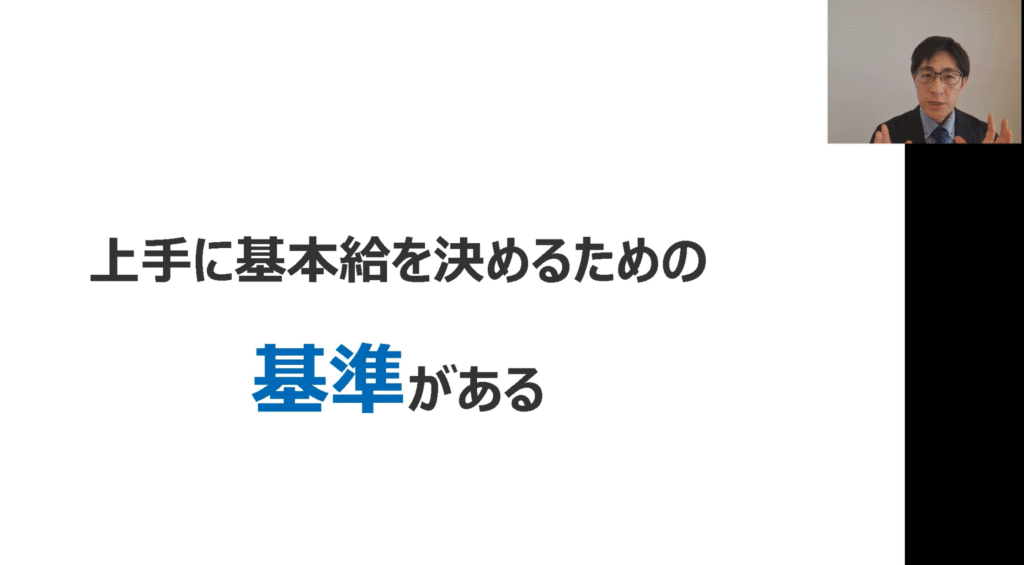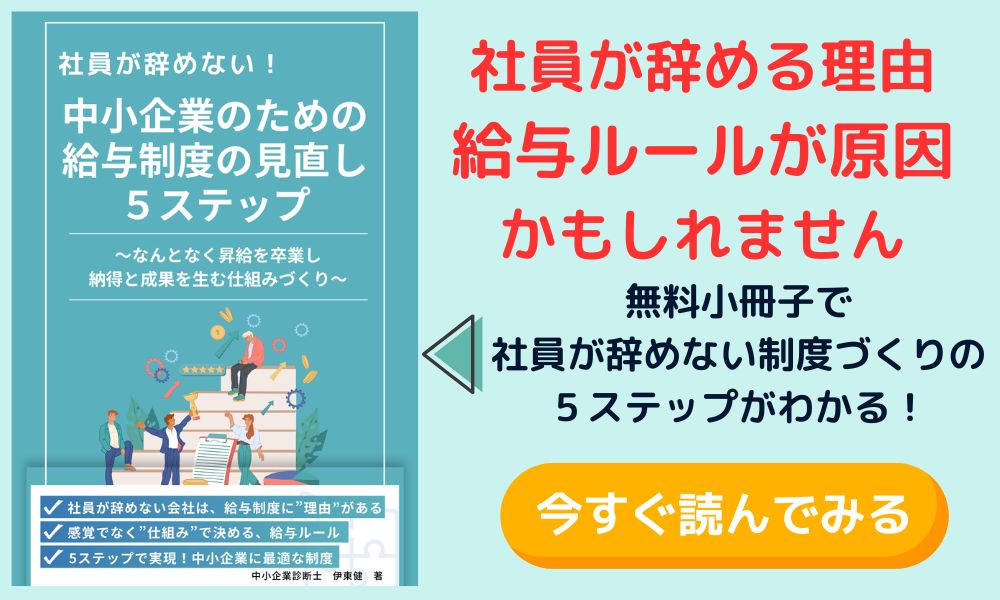【完全ガイド】給与制度見直しの手順と成功事例
給与制度見直しの重要性を理解し、給与制度見直しをどのように成功させるかについて、事例を交えながら紹介していきます。
本記事では、給与制度とそのメリットについて説明し、企業の成長・発展における役割や、人材確保やモチベーション向上につながるポイントを解説します。
また、具体的な手順や注意点に加え、成功した給与制度改革の事例も紹介します。
この記事をご覧いただくことで、あなたの会社の給与制度見直しや人材育成に役立てることができると考えています。
1.給与制度見直しの重要性とメリット
1-1. 給与制度見直しはなぜ必要? 失敗しないためのポイント
給与制度の見直しは、企業の成長と従業員のモチベーション向上に不可欠です。特に、中小企業では限られたリソースの中で最大限の成果を上げるために、適切な給与制度を構築することが重要になります。

企業にとって給与制度は単なる支払いの仕組みではなく、経営戦略の一環として機能します。適切な給与制度が整っていれば、優秀な人材の確保・定着が可能になり、社員の働く意欲が高まります。逆に、不適切な制度が放置されると、組織の成長を妨げる大きな要因になり得ます。
たとえば、以下のような課題がある場合、給与制度の見直しが必要なサインかもしれません。
- 市場と比較して給与が低い場合 → 優秀な人材の流出が加速し、採用難に直結する
- 評価制度と給与が連動していない場合 → 社員の不満が増加し、離職率が上昇するリスクが高まる
- 昇給ルールが曖昧な場合 → モチベーション低下を招き、業績向上の妨げになる
- 給与体系が不透明で不公平感がある場合 → 社員間の不信感が高まり、組織の一体感が損なわれる
これらの問題を解決するためには、自社の経営戦略に沿った給与制度の見直しが必要です。具体的には、競争力のある給与水準を設定し、評価制度と適切に連動させることが重要になります。
1-2. 給与制度を見直すとどう変わる? 成功事例から学ぶメリット
給与制度を見直すことで得られるメリットは数多くあります。適切な制度の導入により、従業員のエンゲージメントが高まり、企業全体の業績向上につながることが期待されます。ここでは、実際に給与制度を見直し、成功した企業の事例を紹介します。
【成功事例】
- 製造業A社(従業員50名): A社は、従来の年功序列型給与体系を見直し、職務・役割に応じた「役割給制度」を導入しました。それまで、勤続年数が長い社員ほど高い給与を受け取っていましたが、業務の責任や貢献度に応じた給与体系に変更することで、社員の責任意識が向上。特に、リーダークラスの社員の主体性が高まり、結果として生産性が15%向上しました。また、新たに昇進を目指す社員も増え、組織全体のモチベーションが向上しました。
- IT企業B社(従業員120名): B社では、個人の成果を正しく評価できていないことが問題視されていました。そこで、成果主義の評価制度と連動した給与制度を導入し、社員の実績やスキルアップが給与に反映されるようにしました。特に、プロジェクトの成果に応じたインセンティブを設けたことで、社員の意欲が向上し、業績が改善。結果として、社員の離職率が30%低下し、安定した人材確保が可能になりました。
- サービス業C社(従業員80名): C社は、給与の大部分を固定給で支給していましたが、社員の営業成績に応じた「業績給制度」を導入しました。これにより、売上目標を意識した行動が増え、成果を上げた社員が正当に報われる仕組みが確立。結果として、営業成績が20%アップし、社内の競争力と士気も向上しました。
- 建設業D社(従業員30名): D社は、給与の決定プロセスが不透明で、社員から不満の声が上がっていました。給与決定の基準を明確にし、評価基準と連動させることで、社員にとって公平感のある制度を実現。これにより、社内のコミュニケーションが円滑になり、離職率が低下しました。
このように、給与制度を適切に見直すことで、社員のモチベーション向上、人材定着、企業の成長といった効果が得られるのです。
1-3. 給与制度を変えないと起こるリスクとは?
給与制度を放置すると、企業の成長や社員の働き方に大きな悪影響を及ぼします。適正な給与制度がない、または時代に合っていない制度を続けていると、さまざまな問題が生じます。
✅ 採用が難しくなる
現在の労働市場では、給与が競争力のある水準にない企業は、優秀な人材を確保するのが非常に難しくなります。特に中小企業の場合、大手企業と比較してブランド力や福利厚生で劣ることが多いため、給与水準が適正でないと応募者が減少し、結果的に採用コストが上昇してしまう可能性があります。

さらに、企業の口コミサイトや転職市場において「給与が低い企業」と評価されると、求職者の応募意欲が低下し、企業イメージの悪化にもつながります。これにより、必要な人材を採用できず、組織の成長が停滞するリスクが高まります。
✅ 社員の不満が高まり、離職率が上昇する
給与制度が適正でない場合、社員の不満が蓄積され、離職率が上昇します。
- 給与が市場より低い → 競合他社へ転職を検討する社員が増える。
- 給与の昇給ルールが不透明 → 努力や成果が評価されていないと感じる。
- 評価制度と連携していない → 「なぜこの人の給与が高く、私の給与は上がらないのか」といった不公平感が生じる。
このような問題が続くと、特に優秀な人材が先に流出し、組織全体のスキルレベルが低下する恐れがあります。また、新しく人材を採用しても、給与制度が改善されなければ、同じ理由で再び離職するケースが増える可能性があります。
✅ 企業の競争力が低下する
給与制度が適正でないと、社員の意欲やパフォーマンスが低下し、以下のように企業の競争力が損なわれることも考えられます。
- モチベーションの低下:給与が適正でない場合、社員は仕事への熱意を失い、「どうせ頑張っても報われない」という考えが広がる。
- 生産性の低下:給与が上がる見込みがないと、社員は現状維持に留まり、新しいスキルを習得しようとしなくなる。
- 業績への影響:低モチベーション・低生産性が続くと、売上や利益にも直接的な悪影響が及ぶ。
特に中小企業の場合、限られた人材で運営されているため、社員一人ひとりの生産性が企業の成長に大きく関わります。適正な給与制度が整っていないと、企業全体のパフォーマンスが悪化し、業界内での競争力を維持できなくなります。
✅ 組織の一体感が損なわれる
給与制度の決定基準が不明確であったり、不公平感があると、組織内の信頼関係が崩れ、社内の雰囲気が悪化し、以下のような問題が生じることもあるでしょう。
- 部署間や職種間で給与の差が大きすぎる → 「同じような業務内容なのに、なぜこんなに給与が違うのか」といった不満が噴出。
- 評価と給与が連動していない → 「努力しても評価されない」という思いから、業務の手を抜く社員が増える。
- 経営側と社員の対立 → 「経営陣ばかりが利益を得ている」という不信感が広がる。
組織の一体感が崩れると、社員同士の協力関係も損なわれ、チームワークが悪化します。結果的に、会社全体の業績や職場環境にも大きな影響を及ぼします。

✅ 法的リスクが高まる
給与制度が適切に運用されていないと、労働基準法違反や訴訟リスクが高まります。
- 最低賃金の引き上げに対応できていない → 違法状態になり、労働基準監督署の指導対象になる。
- 残業代未払い問題 → 労働時間管理が適正でないと、未払い賃金が発生し、労働トラブルに発展する。
- 雇用契約と実際の給与のズレ → 雇用契約書と実際の給与支払いに差異があると、社員から訴えられる可能性がある。
給与制度の不備が原因で法的トラブルが発生すると、企業の信用が失われるだけでなく、高額な賠償金や罰則を科されるリスクもあります。
2.給与制度とは? 中小企業のための基本ガイド
2-1. 給与制度の基礎知識|基本給・手当・賞与の違い
給与制度とは、企業が従業員にどのように賃金を決定し、支払うかを定めた仕組みです。適切な給与制度は、企業の経営戦略や従業員の働き方に大きく影響を与えるため、慎重に設計する必要があります。
給与の主な構成要素は、大きく 「基本給」「手当」「賞与」 の3つに分けられます。
✅ 基本給(昇給を含む)|職務・能力・経験に応じた固定給
基本給は給与の中核をなす部分で、従業員の職務、能力、経験などに応じて決定されます。企業の給与制度によって、以下のような考え方で決定されます。
- 年功型の基本給:長期雇用を前提とし、年齢や勤続年数に応じて昇給する。
- 職能型の基本給:従業員のスキルや能力に応じて決定・昇給する。
- 職務型の基本給:担当する業務の難易度や責任の大きさに応じて決定される。
- 役割給(役割に応じた基本給):管理職や専門職など、特定の役割に応じて設定される。
昇給の仕組みも重要で、年次昇給や評価による昇給、役職昇格による昇給など、企業の方針によって異なります。
✅ 手当|基本給を補完し、特定の条件に応じた支給額

手当は、基本給とは別に特定の条件を満たした場合に支給される給与の一部です。代表的な手当には以下のようなものがあります。
- 役職手当:管理職など特定の役職に就く従業員に支給。
- 資格手当:業務に必要な資格を取得している従業員に支給。
- 通勤手当:交通費を補助するために支給。
- 住宅手当:家賃補助として支給される手当。
- 家族手当:扶養する家族の人数に応じて支給。
- 時間外手当(残業代):法定労働時間を超えた勤務に対して支給。
手当は企業の方針によって設定されるため、制度設計の際には目的を明確にし、必要なものだけを採用することが重要です。
✅ 賞与|業績や成果に応じた変動給
賞与(ボーナス)は、企業の業績や個人の成果に応じて支給される報酬で、通常は年に1~2回支給されます。
- 定期賞与:夏・冬など、決まった時期に支給される。
- 業績連動賞与:会社の業績や利益に応じて変動する。
- インセンティブ(成果報酬):営業成績や目標達成率に応じて支給。
賞与は、従業員のモチベーション向上や業績向上のために活用されますが、支給基準が明確でないと不満につながることもあるため、制度設計には注意が必要です。
2-2. 中小企業に最適な給与制度とは? 3つの設計ポイント
中小企業にとって、適切な給与制度を設計することは、事業の成長や従業員の定着率向上に直結します。以下の3つのポイントを押さえておくことで、効果的な給与制度を構築することができます。
✅ 公平性の確保:透明な評価基準を設ける
給与がどのように決定されるのかについて、そのルールや根拠(明確な評価基準)を社員に説明できるようにすることが重要です。「誰が、どのような基準で昇給するのか?」が分からないと、不公平感が生まれ、モチベーション低下につながってしまいかねません。

例えば、定量評価(売上・業績など)と定性評価(スキルアップ・リーダーシップなど)を組み合わせた明確な評価基準を設定し、その結果を昇給や賞与の決定の根拠とすることです。
✅ 柔軟性の確保:市場変動に対応できる制度
給与制度は一度決めたら終わりではなく、定期的に市場の変化に応じて見直すことが重要です。特に、中小企業では外部環境からの影響の度合いが大きく、また業績変動も多きことが多いため、「固定給+業績給」のバランスを調整できる仕組みが有効です。
例えば、基本給は生活保障の意味合いで世間相場から最低ラインを超える水準に設定し、賞与で業績を一定程度反映するような仕組みを作ることができます。
固定給については世間相場とも比較しながら、自社の給与水準が適正かどうかもチェックし、必要に応じて調整を行うことが重要です。
✅ 成長を促す設計:キャリアアップに応じた昇給ルール
昇給が単なる「年功的な自動昇給」ではなく、キャリアアップやスキル向上と連動していることが望ましいです。
例えば、スキル習得や資格取得、社内における貢献の度合いに応じて昇給の格差を設定するという仕組みが考えられます。
「経験を積むだけで昇給する」のではなく、「貢献度やスキルアップが正しく評価される」仕組みを作ることで、社員のモチベーション向上につながることでしょう。
3.給与制度を見直す際に考えること
3-1. 給与制度を変えたら社員はどう思う? 反発を防ぐ方法
給与制度の変更は、社員にとって大きな関心事であり、誤った進め方をすると反発を招く可能性があります。スムーズに移行するためには、以下の対応が有効です。
✅ 事前の説明会を必ず実施する

給与制度の変更に関する説明会を開き、目的や背景、メリットを伝えます。社員が不安を感じないように、具体的な変更点とその理由を明確に説明しましょう。
✅ 社員の意見を取り入れ段階的に変更することも視野に入れる
いきなり大幅な変更を行うと、社員の混乱を招きます。まずは意見をヒアリングし、試験的に一部の変更を導入するなど、段階的な対応を検討しましょう。
✅ 評価制度との連携を強化する
給与制度の変更と評価制度の見直しをセットで行うことで、公平性を保つことができます。社員が納得できる評価基準を整備し、それに基づいた給与決定を行いましょう。
3-2. 中小企業が給与制度を見直すときの「落とし穴」5選
給与制度の見直しは慎重に行わないと、かえって社内に混乱を招くことがあります。特に以下の5つのポイントには注意が必要です。
✅ ポイント1.社員への説明不足 → 反発を招く
給与制度の変更は社員の生活に直結するため、説明が不十分だと強い反発を受ける可能性があります。事前に説明会を実施し、納得感を持たせることが重要です。
✅ ポイント2.市場給与と比較せずに決定 → 人材流出リスク
自社の給与水準が市場相場と合っていないと、優秀な社員が競合他社に流出するリスクがあります。定期的に市場調査を行い、適正な給与設定を心がけましょう。
✅ ポイント3.評価制度と連携しない → 不公平感が増す
評価制度と連動しない給与制度では、努力や成果が適切に報酬に反映されず、不満が蓄積します。公平な評価基準を確立し、給与決定に反映させることが必要です。
✅ ポイント4.昇給のルールが曖昧 → 社員のやる気低下
昇給の基準が明確でないと、社員は「頑張っても報われない」と感じ、モチベーションが低下します。昇給のルールを明文化し、透明性を確保しましょう。
✅ ポイント5.コスト管理が不十分 → 企業経営に悪影響
給与制度の見直しによって人件費が増加し、経営を圧迫するケースもあります。給与体系の変更前にシミュレーションを行い、持続可能な制度を設計することが重要です。
4.中小企業のための給与制度見直し【完全ロードマップ】
給与制度の見直しは、単なる調整ではなく、企業の成長戦略の一環として進める必要があります。本章では、成功企業の事例をもとに、具体的な進め方を【STEP1】から【STEP5】までのロードマップとして解説します。
【STEP1】現状の給与制度をチェック|5つの診断ポイント
給与制度を見直す第一歩は、現状の問題点を明確にすることです。以下の5つのポイントをチェックし、自社の給与制度が適正かどうかを確認しましょう。
✅ 世間相場と比較して適正な給与か?
自社の給与水準が市場平均と比べて適切かを確認することは、給与制度の見直しにおいて重要です。まず、公的機関の統計データや業界団体、求人情報サイトを活用し、同業界・職種・経験年数ごとの給与水準を調査しましょう。自社の給与が相場より低ければ人材流出のリスクが高まり、高すぎれば企業の利益を圧迫する可能性があります。
✅ 社員の評価が正しく反映されているか?
評価制度と給与が連動していないと、社員のモチベーション低下につながります。成果に応じた報酬制度が整備されているか、昇給のルールが明確かを確認し、公平で納得感のある仕組みを構築することが重要です。
✅ 給与体系が透明で分かりやすいか?
社員が給与決定のプロセスを理解しているかを確認し、不明確な手当や昇給基準がないかを見直しましょう。透明性を高めることで、公平性を確保し、社員の納得感を向上させることが重要です。
✅ 昇給・昇格の基準が明確か?
年功序列に偏らず、スキルや成果に応じた昇給が可能かを確認しましょう。昇格・昇給の条件が明確であることが、社員の成長意欲と公平性の確保につながります。
✅ 企業の財務状況とバランスが取れているか?
人件費の増加が企業の利益を圧迫していないかを確認し、持続可能な給与制度を設計することが重要です。適切なコスト管理を行い、バランスの取れた運用を目指しましょう。
【STEP2】新しい給与制度の方向性を決める(基本給の基準・諸手当・昇給ルールなど)

新しい給与制度を設計する際は、基本給の基準、諸手当の設定、昇給ルールの明確化が重要なポイントとなります。まず、基本給の基準を決める際には、職種ごとの役割や責任範囲を明確にし、それに応じた給与レンジを設定することが必要です。
次に、諸手当の見直しも重要です。不明確な手当がある場合は、その目的を再検討し、必要なものだけを残すことで、給与体系の透明性を向上させましょう。例えば、役職手当や資格手当、通勤手当など、社員の貢献度や業務遂行に直結する手当を適切に設定することが求められます。
さらに、昇給ルールを明確にすることで、社員のモチベーション向上につながります。年功序列ではなく、スキルや成果に応じた昇給が可能な仕組みを整え、評価制度と連動させることが重要です。昇給基準を具体的に定め、社員が自身の成長と給与の関係を理解できるようにすることで、公平で納得感のある制度を構築できます。
【STEP3】モデル給与の作成
モデル給与とは、社員の働きぶりや昇格スピードによって給与がどのように変化するかを示した基準のことです。これを明確にすることで、社員が自身のキャリアプランを描きやすくなり、成長意欲を高めることができます。
モデル給与を作成する際のポイントは、「基本給の昇給」と「昇格による給与アップ」の2つです。基本給は、評価結果などに応じて定期的に上昇させる仕組みを作ります。例えば、標準的な昇給率を年3%とし、高評価の社員には5%昇給を適用するなど、成果に応じたメリハリのある運用が効果的です。

次に、昇格や昇進による給与変動についても明確にします。等級制度を導入し、一定の評価基準を満たした社員が昇格できる仕組みを整えます。例えば、ステージ1(新人レベル)からステージ2(一人前レベル)に昇格すると給与が5万円アップする、ステージ3に昇格するとさらに7万円増えるといったルールを設定することで、社員の成長を促進できます。
このように、モデル給与を具体的に示すことで、社員がどのように努力すれば給与が上がるのかを理解しやすくなり、公平で納得感のある給与制度を構築できます。
【STEP4】評価制度と連動させる|適切な評価×給与の考え方
給与制度を適切に機能させるためには、評価制度との連動が不可欠です。評価が給与にどのように反映されるのかを明確にすることで、社員の納得感を高め、公平性のある報酬体系を構築できます。
一般的には、評価基準を「定量評価」と「定性評価」の2つに分けて設計します。定量評価は売上や業績、達成目標など、数値化できる要素を基準とし、公正な指標を用いることで客観性を確保します。一方、定性評価では、スキル向上、チームワーク、リーダーシップといった数値化しにくい要素を評価対象とします。これらを組み合わせることで、バランスの取れた評価制度を作ることができます。
次に、評価結果を給与にどのように反映させるかを明確にすることが重要です。例えば、評価結果に応じて昇給率を決定する仕組みを導入し、高評価の社員は昇給率が高く、標準評価の社員は緩やかな昇給とするなど、明確なルールを設けます。また、評価と給与の関係を社員に分かりやすく説明し、納得感を持たせることが大切です。

最後に、評価の透明性を確保するため、上司と部下の面談を定期的に実施し、評価の根拠を共有する仕組みを作ることが望ましいです。これにより、評価に対する納得感が高まり、社員の成長意欲を引き出すことができます。
【STEP5】社員説明&導入|トラブルを防ぐコミュニケーション術
給与制度の変更は、社員にとって大きな影響を与えるため、スムーズな導入には丁寧なコミュニケーションが欠かせません。適切な説明と対応を行うことで、不安や誤解を防ぎ、制度の定着を促すことができます。
まず、制度変更の目的を明確に伝えることが重要です。なぜ給与制度を見直すのか、企業がどのような課題を解決しようとしているのかを具体的に説明しましょう。例えば、「社員の努力を正当に評価するため」「市場水準と整合性を持たせるため」など、納得感のある理由を示すことで、社員の理解を得やすくなります。

次に、全社員向けの説明会を実施し、制度の概要を伝えた後、個別面談を行い、それぞれの給与がどのように変わるのかを丁寧に説明することが望ましいです。特に、給与が下がる社員がいる場合には、その背景や今後の成長によって改善される仕組みをしっかり説明し、不満が生じないよう配慮が必要です。
また、いきなり全社導入するのではなく、一部の部署や役職で試験運用を行い、社員の意見を反映しながら調整を加えることも効果的です。フィードバックを受け入れ、必要に応じて修正を行うことで、社員の納得感を高め、円滑な制度導入が可能になります。
最後に、制度導入後も定期的にフォローアップを行い、疑問や不安を解消する機会を設けることが大切です。説明不足によるトラブルを防ぎ、社員が安心して新制度に適応できるよう、継続的なコミュニケーションを心がけましょう。
おわりに
いかがでしたか?
給与制度の見直しは、単なる人件費調整ではなく、企業の成長と社員のモチベーション向上に直結する重要な経営戦略の一つです。
本記事で紹介したステップを参考に、自社の課題を整理し、最適な制度へと改善していきましょう。社員が納得し、安心して働ける給与制度を整えることで、企業の競争力向上にもつながります。
ぜひ、今回の内容を実践し、より良い職場環境を実現してください。