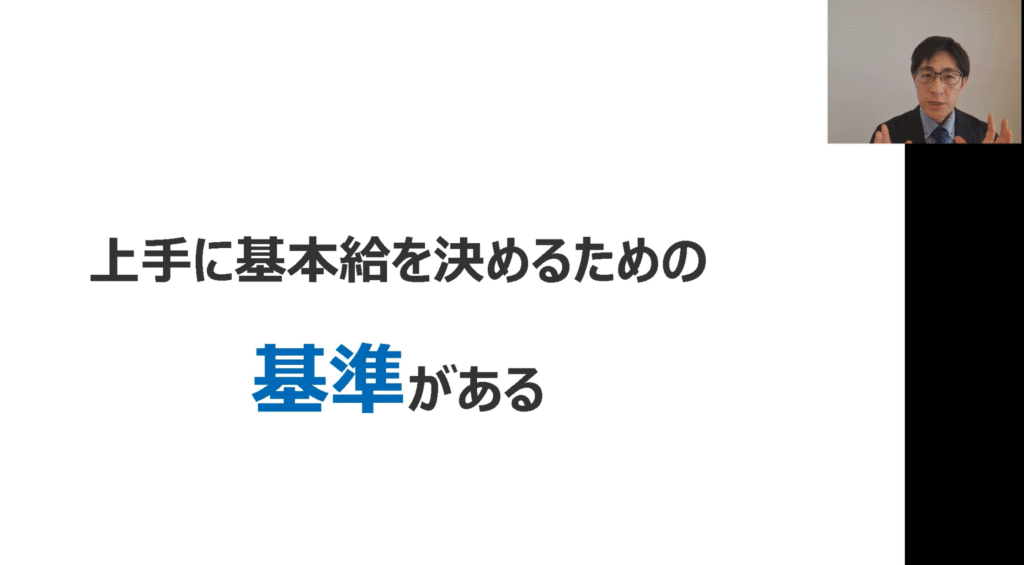『評価項目が抽象的すぎると社員は動けない?改善のヒント』
こんにちは!
給与人事制度構築コンサルタント の伊東健です。
本日は
『評価項目が抽象的すぎると社員は動けない?改善のヒント』
をテーマにお届けします。
「評価シートはあるけど、社員が行動に移してくれない…」
「評価の意味が伝わっていない気がする…」
こうしたお悩みを聞くことがあります。
その原因のひとつが、
“抽象的すぎる評価項目” です。
たとえば、「主体性」「協調性」「業務遂行力」など、
一見もっともらしく見える評価項目でも、
具体的な意味や期待する行動が伝わっていなければ、
評価される側は動けません。
今回は、
そんな“抽象評価”の問題点と
改善のヒントをお伝えします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
抽象的な評価の問題点
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【問題点1】不公平感が生まれる
例えば、評価者によって
「主体性」の解釈がバラバラだとします。
すると、
ある上司は「積極的に提案すること」、
別の上司は「一人で判断できること」
が大事と考えます。
これでは評価に差が出てしまい、
「なぜ自分は低く評価されたのか?」
という納得感のない結果になってしまいます。
【問題点2】やる気が低下する
抽象的な評価では、
「結局、何を頑張れば評価されるのか」
がわかりません。
頑張っても報われないと感じれば、
社員のモチベーションは確実に下がります。
【問題点3】育成につながらない
評価は、本来“成長のきっかけ”に
なるべきもの。
しかし、評価項目が曖昧だと、
「どこを伸ばせば良いのか」が見えず、
成長支援ができません。
では、このような問題を解消して
良い評価項目を設定するにはどうすれば
よいのでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
良い評価項目の3つの条件
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
評価項目を改善するには、以下の3点を意識しましょう。
①具体性
→「どういう場面・行動を評価するのか」
が明確か?
②行動性
→「結果」だけでなく、「過程や行動」にも
焦点を当てているか?
③期待基準の明示
→「どの程度できていれば合格か」を
言語化できているか?
このような点を押さえたうえで、
評価項目をより良いものにするには、
次の3つのステップで進めると効果的です。
【ステップ1】抽象項目の洗い出し
まずは現行の評価シートをチェックし、
「曖昧な言葉」「人によって解釈が分かれそうな項目」
をピックアップします。
【ステップ2】現場ヒアリングをもとに具体化
該当項目について、
「具体的にどういう行動のことを指しているのか?」
現場の評価者・被評価者にヒアリングしてみましょう。
【ステップ3】行動例や期待値を言語化
例えば「協調性」であれば、
・チーム内で報連相ができている
・会議で他人の意見を受け入れる発言ができている
といったように、「見える行動」に落とし込みます。
あわせて、「4(期待を超える)」「3(期待通り)」「2(やや不足)」など、
評価レベルに応じた行動例や水準も明示できると、より効果的です。
いかがでしたでしょうか?
評価項目が曖昧だと、
せっかく制度を整えても、うまく機能しません。
「社員が評価を意識して動く組織」にしていくためには、
“具体的で、動ける評価項目” がカギになります。
評価項目の見直しは、
制度改善の中でも効果が出やすい部分です。
ぜひ、今回の内容を参考に、
自社の評価シートをチェックしてみてください。
今回もご覧いただきありがとうございました。