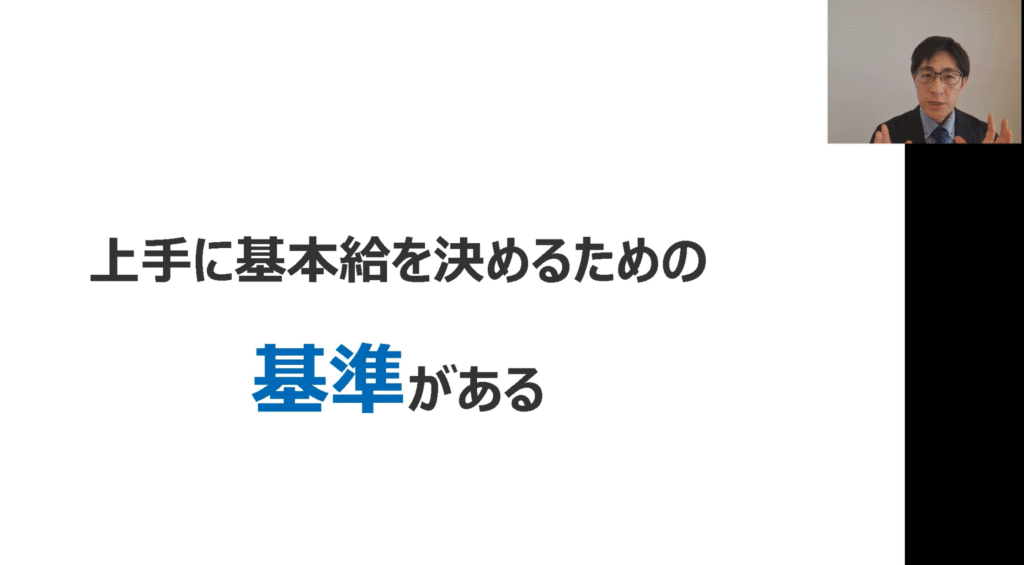「評価者によって結果がバラバラ…」を防ぐ3つの実践策
こんにちは!
給与人事制度構築コンサルタント の伊東健です。
本日は
『「評価者によって結果がバラバラ…」を防ぐ3つの実践策』
をテーマにお届けします。
「同じように働いているのに、評価に差がある」
「上司によって評価の厳しさがバラバラ」
こんな社員の声、聞いたことはありませんか?
評価をしている会社では、本当によくあることです。
評価の“ばらつき”は、評価制度の信頼性を大きく損ってしまいます。
特に中小企業では、評価者の人数が限られている分、
一人ひとりの評価の仕方がそのまま社員の納得感に直結します。
今回は、
そんな評価のばらつきを防ぐための実践的な工夫をご紹介します。
まず、評価のばらつきについて
どんな問題が生じるのかみてみましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆評価のばらつきがもたらす3つの問題
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
問題①:社員の不信感が増加
「上司によって判断が違う」と感じた時点で、
評価制度への信頼が失われてしまいます。
問題②:モチベーションの低下
「頑張っても報われない」と感じる社員が出てしまい、
行動意欲が落ちてしまいます。
問題③:組織としての一貫性が損なわれる
評価がブレていると、
人材育成の方針や報酬の基準もブレてしまいます。
評価のばらつきについてですが、
もちろん意図して問題を起こしている
というわけではないはずです。
よくあるのが以下のような
運用をしているために
結果としてばらつきが大きくなるケースです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆よくある評価の運用上の問題点
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
問題①:評価基準の解釈が個人任せ
評価シートに同じ言葉が書かれていても、
「何を見て判断するか」は評価者によって違います。
たとえば「主体性」を「自分で判断して行動すること」
と考える人もいれば、「上司に言われる前に動くこと」
と捉える人もいます。
問題②: 評価経験の差が大きい(特に昇進したばかりの管理職など)
管理職になりたての評価者は、
評価の基準や面談の進め方に
慣れていないケースが多いです。
また、評価の方法や面談の有効な仕方の
教育が不十分で、感覚や主観頼りになる
ということがよくあります。
結果として、厳しくなりすぎたり
甘くなりすぎたりする傾向があります。
問題③:「評価=点数づけ」だと思っている
評価期間が終わる直前になって評価シートが配られ、
「とにかく点数をつけて提出すること」
が優先されてしまうケースは少なくありません。
このような運用では、評価は“成長のための対話”ではなく、
単なる「点数づけ作業」になってしまいがちです。
こうした問題を放置すると、制度の形だけが残り、
「評価されても納得できない組織」になってしまいます。
ではどうすればよいのでしょうか?
評価のばらつきを防ぐ3つの工夫を
お伝えします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ 評価のばらつきを防ぐ3つの方法
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
方法①:評価項目に「定義」と「具体例」を加える
評価項目の言葉だけでは、
評価者ごとに解釈が異なりやすくなります。
たとえば「主体性」という項目があった場合、
A課長は「自分で考えて提案すること」
B課長は「上司の指示がなくても動けること」
と、捉え方がバラバラになりやすく
評価の公平性が損なわれます。
そこで重要なのが
「定義」や「行動例」などの
説明を加えることです。
たとえば:
・主体性:自ら課題を見つけ、
上司に相談のうえ提案・行動している
・チームワーク:他メンバーの状況を把握し、
声かけやフォローができている
このように、誰が見てもブレが起きにくい表現
にすることで、評価者ごとの差を小さくできます。
方法②:評価者同士での「すり合わせ」の場を設ける
点数をつけたあと、評価者同士で
「この評価は妥当か?」を共有・確認し合う場を持つことで、
評価の甘辛や基準のズレを是正できます。
特に、次のようなポイントで話し合うと効果的です。
・評価の判断理由を言語化し、共有する
・他の評価者の視点や基準を知る
・評価項目の解釈や使い方で迷っている点を相談する
これは「キャリブレーション(目線合わせ)」と呼ばれ、
評価の質を高める定番の方法です。
方法③:評価者向けの継続的なミニ研修・ガイダンス
評価制度を導入したタイミングだけでなく、
評価のタイミングごとに簡易な研修やガイドを
実施することで、評価のブレを予防できます。
・評価の目的を再確認
・よくある解釈の違いを共有
・面談の基本的な進め方を復習
・評価シートの改善点を意見交換
年1回の研修だけでなく
「15分でもいいので定期的なリマインド」が有効です。
忙しい管理職でも負担なく取り組める
仕組みにするのがポイントです。
いかがでしょうか?
評価制度は、制度そのものよりも
“誰が、どのように評価するか”が重要です。
評価者の判断がブレると、
どんなに立派な制度を作っても、
社員の納得感にはつながりません。
もし「上司間の評価がばらつき納得感が高まらない…」
というお悩みがある場合は
ぜひ今回ご紹介した3つの工夫を
取り入れてみてください。
今回もご覧いただきありがとうございました。